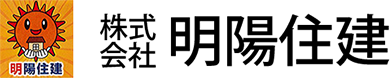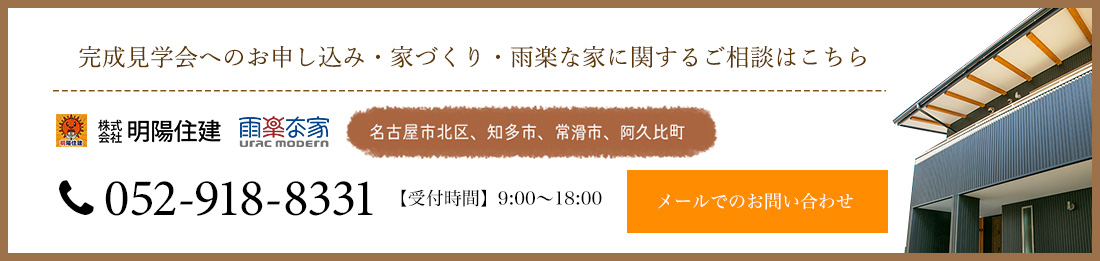2025年建築基準法の改正で家づくりはどう変わる?押さえておきたいポイント
目次
2025年4月に建築基準法の大幅な改正が予定されています。この改正は、家づくりを考えている人にとっても大きな影響を与える内容になっています。特に自然素材を活かした木の家を検討している方にとって、今回の改正はどのような意味を持つのでしょうか?
本記事では、建築基準法の基本的な役割を整理しながら、2025年の改正ポイントを詳しく解説します。特に木の家を建てる際に知っておくべき重要なポイントを中心に紹介するので、これから家を建てたいと考えている方はぜひ参考にしてください。

建築基準法とは?家づくりにどのような影響があるのか?
建築基準法は、建築物を建てる際の最低限の基準を定めた法律であり、その目的は建物の安全性を確保し、国民の生命・健康・財産を守ることです。新しく家を建てる場合は、この法律を必ず守る必要があります。
具体的なルールとして、例えば以下のようなものがあります。
・接道義務:敷地が幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない
・容積率・建ぺい率・高さ制限:建築可能な建物の大きさを制限
・用途地域:エリアごとに建てられる建物の種類を制限
・防火地域・準防火地域:防火性能が求められるエリアでの建築基準
このようなルールは、家づくりにおいて必ず考慮しなければなりません。そして、2025年の改正ではさらに厳格な規制が追加される予定です。
2025年建築基準法改正の背景
今回の改正の目的は、大きく分けて「省エネ性能の向上」と「建物の安全性の強化」です。日本のエネルギー消費の約3割は建築物が占めており、国としてカーボンニュートラルを推進するために、住宅の省エネ化をより強く求めるようになりました。
また、最近では大空間を持つ住宅や環境負荷の少ない家づくりが進められています。しかし、建築物の重量が増加することで、耐震性の確保がより重要になっています。そのため、2025年の改正では、以下の3点が大きく変わります。
- 四号特例の見直し
- 構造計算の義務化対象の拡大
- 必要な耐力壁の増加
これらの変更は、今後の家づくりに大きな影響を及ぼすことが予想されます。
2025年の建築基準法改正で変わること
四号特例の見直し
これまで、小規模な木造住宅(平屋や2階建ての住宅)は「四号特例」により、一部の建築確認審査が省略されていました。しかし、2025年4月からはこの審査省略制度が廃止され、200㎡を超える木造建築物では構造関係の審査が義務化されます。
これにより、審査に必要な書類の提出が増え、確認申請の手続きが煩雑になる可能性があります。また、今までよりも設計や施工の自由度が下がることも考えられます。
構造計算の義務化対象の拡大
これまで、延床面積500㎡以下の木造建築物については、「壁量計算」という簡易的な計算のみで安全性を確認していました。しかし、2025年の改正後は、この基準が「延床面積300㎡超」に引き下げられます。
これにより、中規模の木造建築物では、従来よりも厳格な構造計算が求められるようになり、設計コストが増加する可能性があります。特に住宅以外の中規模建築物において、コスト削減を目的にしていたケースでは、大きな影響を受けることになるでしょう。
必要な耐力壁の増加
木造住宅のZEH化(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)により、断熱材や高性能サッシ、太陽光パネルの導入が進んでいます。しかし、それによって建物の重量が増加し、耐震性を確保するために、必要な耐力壁の量が1.6倍に増加することが決まりました。
これにより、大開口のリビングや吹き抜けのデザインが制限され、間取りの自由度が下がる可能性があります。また、使用する木材の量が増えることで、建築コストが上昇することも考えられます。
木の家への影響は?自然素材の家づくりはどうなる?
自然素材を活かした木の家を建てたいと考えている方にとって、2025年の法改正はどのような影響をもたらすのでしょうか。
木造住宅の設計自由度が下がる
必要な耐力壁の量が増えるため、吹き抜けや大開口の設計が難しくなります。特に、自然素材を活かした開放感のある設計を考えている場合、従来のプランでは対応できない可能性があるため、事前にしっかりと相談することが重要です。
無垢材の活用が増える可能性
今回の改正では、集成材よりも無垢材が有利になる可能性があります。集成材は接着剤を使用するため、重量が増える傾向がありますが、無垢材は軽量でありながら高い強度を持つため、構造計算の観点からも採用しやすくなるでしょう。
建築コストの増加
審査書類の増加や構造計算の義務化により、設計・施工コストが増加することが予想されます。また、耐力壁の増加に伴い、建築資材の使用量も増えるため、住宅の価格が上昇する可能性があります。
2025年以降の家づくりで押さえておきたいポイント
2025年以降に家を建てる場合、次の3つのポイントを意識すると、改正の影響を最小限に抑えながら理想の家づくりができます。
- 事前に設計相談をしっかり行う
- 無垢材を活用することで耐震性とコストのバランスをとる
- 初期費用とランニングコストのバランスを考慮する
まとめ
2025年4月の建築基準法改正により、家づくりのルールが大きく変わります。特に木造住宅に関しては、四号特例の見直しや構造計算の義務化、必要耐力壁の増加などが影響を与え、設計やコストに変化が生じるでしょう。
木の家を建てる際は、改正後の基準に対応できる設計を意識しながら、無垢材の活用や事前相談をしっかり行うことが重要です。長く快適に住める家を建てるために、最新の情報を押さえておきましょう。